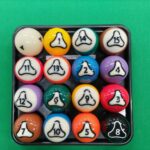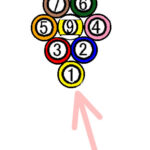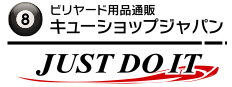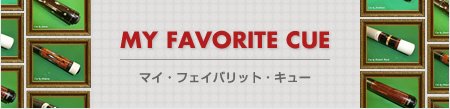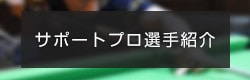こんにちは、スタッフ野田です。
羅立文(ローリーウェン)プロによる14-1解説動画その23です。
例によって1球ずつ次に何をしたいかを説明しながら撞いてもらっています。
それでは早速動画をご覧いただきましょう。
今回の配置は前回と全く同じで、ブレイクボールがフット側コーナー穴前にある配置ですが、
手球の位置が異なっています。

ブレイクボールはコーナーポケット穴前で、前回はこれを上から狙う配置でしたが、今回は手球がフットレールの中央付近にあり、横からブレイクボールを狙います。
最初にお断りしておきますが、これはなるべく避けるべき配置で、前回のようにブレイクボールを上から狙って、フット側にワンクッションさせてブレイクする方が安全です。
上からの場合はラック底辺の遠い方(この例では⑨⑩あたり)を狙ってスクラッチの回避と手球をテーブル中央に戻すことが期待できます。
しかし今回のように横から長クッションへワンクッションさせてラックに当てる場合、そのような調整をすることが難しくなります。
ラック底辺の角にある的球(今回は⑬)を狙うのですが、強く撞いてこの的球の正面に手球を正確に当てるのは至難の業です。下に当たれば手球はフット側に落ちてしまい、悪くすれば左手前コーナーにスクラッチしますし、上に当たれば手球はヘッド側に向かい、次に遠い的球しか狙えなくなる可能性が大きいのです。
ただ、もしブレイクボールがポケットの中で長クッション側に寄っていたら、上からではポケットの角を避けるために薄く狙うことができなくなり、手球を強くラックに当てることが難しくなります。したがって不利を承知でこのような狙い方をせざるを得なくなるのです。

ブレイク後の配置です。
手球は⑬の正面に見事に当たりました。さすが羅プロといったところですが、毎回これほど上手く
当たることはないそうです。
⑬の正面に当たったおかげで、ラックは適度に散り、手球はあまり大きく動かずテーブル中央付近に留まり、いくつかの的球が狙える配置となりました。理想的なブレイクと言えるでしょう。
羅プロは⑩を入れて次に⑦を入れながらラック範囲内にあるクラスターを散らしにいくことを考えました。

うまく⑦を右フリにする位置にポジションできました。
クラスターを構成する的球は3個だけなので、ゆっくり撞くだけで十分散らせます。
むしろ強く撞くと散らした的球が他の的球にくっついて新たなクラスターを形成する可能性があるので、3個の的球の行方を考えて散らす力加減を調整します。
また、ゆっくり撞けば次に⑨・⑪・⑬が狙える可能性が高いことにも注目してください。

⑦を入れたところです。
クラスターはきれいに散り、複数の的球が狙える状態となりました。
ブレイクボールの候補も複数あり(⑥か⑫が最有力)一安心といったところですが、このように多くの的球がきれいに散っている場合は下手に的球を動かすと新たなクラスターを作り出してしまう可能性があるので、手球の動きが必要最低限になるようにして慎重に取り切りを続けます。
まずはサイドにまっすぐな②を取り、次に③を狙います。

②をストップショットで入れたところです。
次に取るのは③で決まっているのですが、ここで羅プロは慎重に配置を検討します。
ご覧の通り的球はきれいにバラバラになっており簡単に取り切れそうに見えますが、わずかな加減のミスで窮地に陥る可能性を常に孕んでいることを肝に銘じておくことが必要です。
のちほど説明しますが、③の次は④を取る予定です。

③を入れたところで、羅プロはブレイクボールを⑫、ブレイクボールにポジションするためのキーボールを⑮と想定しました。先ほど慎重に配置を検討した時点でこれを決めていました。
次は④か⑨が狙えますが、羅プロは③を入れる前から次は④を狙うと決めていました。
これは右端にある⑥を取りやすくするために④を片づけておきたいからです。
⑥は④を右手前コーナーに取るためのブロックボールとなっており、逆に④は⑥をコーナーに取るためには邪魔なので、このどちらかを早めに処理しておきたいのです。
なお、⑥はブレイクボールの第2候補なので、⑫でブレイクすることが難しくなった場合に備えて可能なら温存しておきたいところです。
最後が⑥と⑫の2個だけになっても、お互いがキーボール・ブレイクボールとなることができます。

④をストップで入れて、次は⑧をサイドに狙います。
⑧から手球をテーブル中央付近に戻します。
1個だけ離れたヘッド側にある⑤をいつ取りにいくかですが、この時点で羅プロはキーボール⑮に
厚くポジションするためのキーキーボールとすることを考えていたようです。

⑧を入れたところです。
残り球の中で取りにくそうなのは⑭で、これはブレイクボールである⑫がブロックボールとなって⑭を左手前コーナーへ入れるコースを妨害してしまっているためです。
そこで羅プロは⑪か⑬のあとに⑭を左サイドへ取ることを考えています。
そこから逆算して⑥→⑨と取り、次に⑪か⑬を厚めになるようにします。

⑥を入れて⑨へポジションしたところです。
⑨の次はワンクッションで⑪か⑬にポジションします。どちらからでもいけるので、これは自分が最も得意な加減でポジションできる方を選べばよいでしょう。

羅プロは⑬へポジションしました。
わずかに左フリなので、手球を少し前へ出して⑪にまっすぐに出します。
⑭を左サイドに取る際に左フリになるのは絶対に避けたいので、⑪に大きな右フリがつかないようにします。

狙い通り⑪はほぼまっすぐとなりました。
ストップショット(スタンショット)で次の⑭を少し右フリにして、⑤へのポジションがしやすいようにします。

⑭に適度な右フリが付きました。次の⑤には左フリを付けて、ワンクッションでキーボール⑮に
ポジションする予定です。
もしフリなしになっても引き球で⑮にポジションできますし、少しなら右フリになっても押しと逆ヒネリで対処できます。

⑤にはわずかに左フリが付いた厚い配置になりました。
実はこれはあまり良いポジションではありません。
キーボール⑮は右フリにしたいのですが、このポジションからでは強く撞いて手球をワンクッションさせなければなりません。強く撞くことは的球が外れたりポジションが悪くなる可能性が増すことを意味します。
少し左フリが足らなかったわけですが、このようなわずかな加減の違いがその後の展開に大きく影響してしまうことがよくあるので、簡単に見える配置でも「このポジションはダメ」という落とし穴を避けるように常に意識する必要があります。しかしこれはまさに「言うは易し、行なうは難し」なのです。

羅プロは強く撞いて⑮への右フリを確保しました。簡単に撞いているように見えますが、実はかなり慎重に狙っています。心の中では「しまった、少し厚かった」と思っていたかもしれません。
もし⑮が左フリになると手球を遠い反対側の長クッションに跳ね返して、ブレイクボール⑫を左フリにする非常に狭い範囲内にポジションするという難しいコントロールショットが必要になってしまいます。
厚めの左フリになったら最悪で、もしそうなったらブレイクボールからラックへのダイレクトヒットは諦めてワンクッションブレイクに切り替えるしかありません。
ブレイクボール⑫はラックから遠く離れているので、なるべく薄い配置にします。
手球が長クッション際に止まるくらいのつもりでちょうど良いでしょう。

⑮を入れて手球をクッションの近くにポジションしました。
この位置からブレイクボール⑫を狙うのは「への字」などと呼ばれる(英語ではバックカットと言います)厚みが見にくいちょっといやな配置となるのですが、ブレイクを成功させるためにはこういったショットをこなしていく必要があります。
克服するには練習あるのみです。
前回のビリヤードエキスポ記事の中でご紹介した、羅プロオススメの HeddaRo MAX チョークが発売となりました。
優れたチョークと機能的なケースの組み合わせでリーズナブルなお値段となっています。
是非お試しください。